
看護部 2011年認定
がんと共に生きる方はたくさんいらっしゃいます。がんと向き合いながら「仕事を続けたい」「趣味を楽しみたい」といった希望や目標を持ち、人生を前向きに生きるためのサポートを大切にしています。そのために、患者さん個々の価値観や大事にしていることを尊重してケアしています。
専門看護師、特定認定看護師、認定看護師は、それぞれ異なる役割を担い、患者のニーズに応じた専門性の高いケアを提供しています。
専門看護師は高度な専門知識を活かして患者全体をサポートし、特定認定看護師は特定の医療行為を行い、認定看護師は日常的な患者ケアを通じて患者の安心を支えます。このチーム医療の中で患者中心の質の高い看護が実現されています。

専門看護師は、特定の看護分野において高度な専門知識と技術を持ち、患者やその家族に対して包括的なケアを提供します。
看護実践だけでなく、教育や研究、政策提言などの役割も担います。専門看護師は、大学院修士課程を修了することが求められ、複雑な看護問題に対処するためのスキルを持っています。

がんと共に生きる方はたくさんいらっしゃいます。がんと向き合いながら「仕事を続けたい」「趣味を楽しみたい」といった希望や目標を持ち、人生を前向きに生きるためのサポートを大切にしています。そのために、患者さん個々の価値観や大事にしていることを尊重してケアしています。

リエゾンナースは身体を病む人への心のケアを実践する専門看護師です。一般病棟に入院している患者さんに対し精神看護の視点からケアを提供するとともに、看護師に対しても教育的・心理的にサポートすることを通じて、包括的に患者さんへのケアの質を高めることを目標にしています。
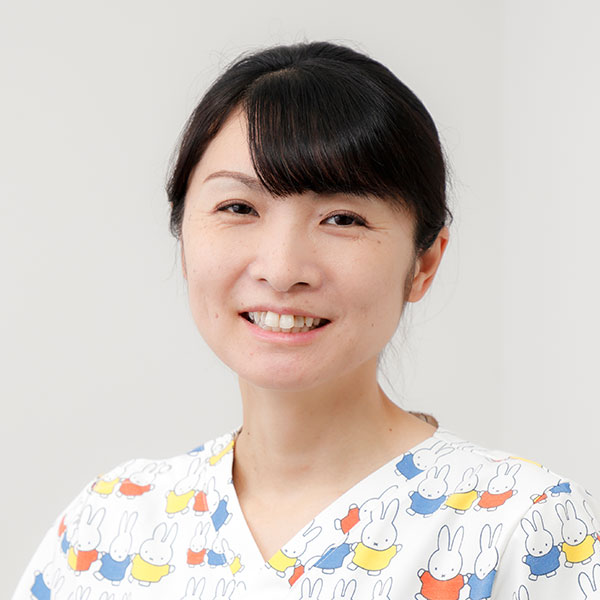
小児科病棟には健康障害や発達段階、家族背景など様々な状況におかれている子どもが入院しており、子どもとその家族の権利を尊重し、子どもたちが健やかに成長・発達していけるよう看護師間や多職種と協働して支援ができるように努めています。

生命の危機的状況もしくはハイリスクな場面において、科学的根拠と患者・家族の思いを統合しニーズを捉え、多職種チームで介入することでより良いケアを実現します。また医療スタッフや組織の困り事に共に取り組んだり教育することで更なる看護の質向上に努めます。

患者さんは、家族のなかで互いに影響し合う生活者でもあります。家族全体を支援する事で、これまで家族が培った力を医療に活かすだけでなく、患者さんの価値や希望を知る事にも繋がります。個人の価値や家族の形が多様化する中で、その人らしさ、そのご家族らしさを大切にできるような医療を、多職種と共に実現できるよう心掛けています。

特定認定看護師は、特定の医療行為に関する専門的な訓練を受けた看護師で、医師の指示の下、特定の診療補助業務を実施します。
クリティカルケアや認知症看護などの専門分野で、患者の急変時に迅速に対応できる能力を持っています。特定認定看護師は、患者の状態に応じて高度なケアを提供し、医療チームと連携して患者の治療を支援します。急変時の対応や緊急の医療行為の実施が主な役割であり、患者の安全を守るために重要な役割を担っています。

救急の現場では短い時間で患者さんの状況を把握し、アセスメントする能力が求められます。患者さんの少しの変化を見逃さず、適切な介入を行い、患者さんに寄り添った看護の実践をスタッフと共に目指しています。不安の大きい患者さんとご家族の精神的サポートも重視しています。

認知症は入院という環境の変化に適応できず治療をスムーズに行えなくなることがあります。その方の思いをくみ取り、ストレスを最小限に抑え、治療後はなじみの生活環境に戻れるよう病棟看護師と一緒に考え、援助していきたいと考えています。

消化器外科病棟に所属し、創傷やストーマ、排泄に問題を抱える患者さんのケアを行っています。皮膚・排泄ケア認定看護師の先輩やスタッフと力を合わせて、患者さんが安心して社会生活を送れるよう、患者さんの立場に応じたケアを心がけています。

認定看護師は、特定の看護分野において高い専門性を持ち、患者に対して質の高い看護を提供することが求められます。
がん化学療法看護や緩和ケア、感染管理などの分野で、患者のケアを直接行い、患者が安心して治療を受けられるよう支援します。認定看護師は、800時間以上の教育課程を修了し、特定の看護技術を駆使して患者の生活の質を向上させることを目指します。患者の状態に応じた適切な看護を実践し、日々の治療をサポートします。

認定看護師を取得した際はスタッフとして実践中心の活動を行ってきました。現在は立場も変わり、指導や教育がメインになっていますが、院内外で活躍できる看護師の育成を目標に取り組んでいます。また現在はEICUに所属しているため、救急搬送された患者さんがどれだけ早期に社会復帰できるか、そのために何をすべきであるかスタッフと考えながら活動しています。

当院がカバーする2次医療圏の住民は約120万人、新宿駅の乗降客は360万人/日です。地域の歯車として救急医療機能を維持するためには、速やかに応需し、救急隊を早く現場に返すこと、Fastトラックエリアの患者滞在時間を短くする必要があります。そのために「5S」「コンフォートケア」「シームレスな救急応需と継続看護」を戦略テーマに各チームで楽しく取り組んでいます。
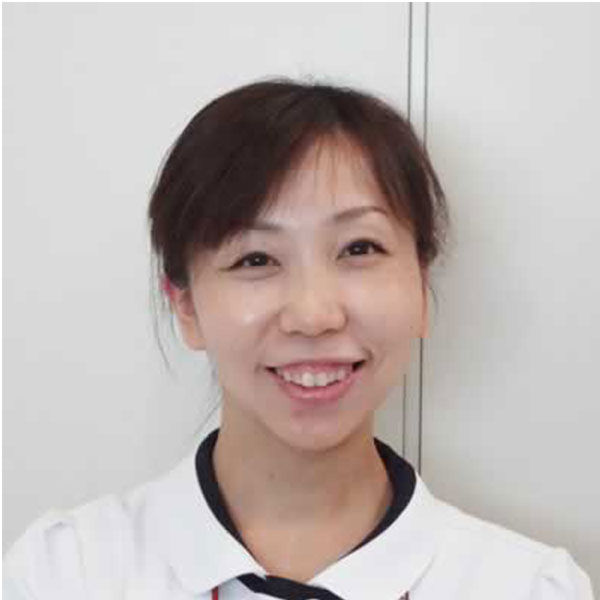
私の目標は、患者さんが望む生活を送れるよう影となって支えることです。創傷やストーマがあってできないではなく、できるようになるためにどうしたらいいか、多職種で考え協力し合って、患者さんの生活が昨日よりもちょっといい明日になるよう活動していきたいです。

現在、形成外科と整形外科をメインとした病棟に従事しています。形成外科では足病に対する多職種アプローチの機会として足のクリニック(足クリ)を始めます。整形外科は脊椎の患者さんが多く、排尿障害に対するケアを実施しています。毎日楽しいです。
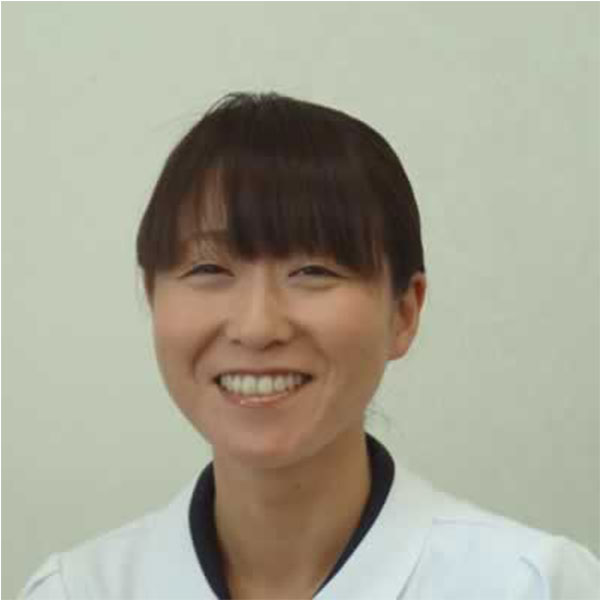
認定看護師として、治療と生活などの多方面から状況をアセスメントし、患者さんとご家族の生活の質を維持・向上できるよう取り組んでいます。患者さん個々の生活、それに関わる人々を支えるため多職種と連携し活動して行きたいと思っています。

ICU・CCUという非日常の中で、患者さんがその人らしい生活を送れるように、知識・技術の引き出しを増やしたくて認定看護師を目指しました。専門的知識を活かして合併症の予防や早期離床に努め、患者さんの早期回復を目指すとともに、日常生活が安楽に過ごせる看護ケアを心がけています。

重篤な状態にある患者さんへもICUからの退室や退院後のQOLが向上できるように多職種とのカンファレンスを通して、スタッフとともによりよい看護ケアを実践したいと考えています。呼吸サポートチームとしては院内の呼吸ケアの質向上を目指して活動しています。

超急性期の患者の看護ケアを実践する上で、患者さんとその家族への声掛けやタッチングをはじめとする直接的な関わりを大切にしています。また、専門領域研修、早期離床・リハビリテーション、RST、RRS等への参画を通した実践・指導・相談から、シームレスな看護を意識しています。

重症患者だからこそ、温かな心のこもった看護を意識し、声なき声を見逃さないことを大切にしています。多職種連携が必須な領域ですが、看護師として何ができるのか常に考えるように努めています。集中治療室に限らず、院内全体の呼吸ケアの向上に向けても取り組んでいます。

『緩和ケア=最期のケア』ではありません。
緩和ケアは疾患だけを診るのではなく、患者さんがその人らしく生活が出来るように支えていくケアです。価値観を知る事でその人らしさに触れる事が出来ます。患者さんが笑顔で生活・闘病が出来るようにスタッフと共に考え看護しています。

がんと共に生きる方はたくさんいらっしゃいます。がんと向き合いながら「仕事を続けたい」「趣味を楽しみたい」といった希望や目標を持ち、人生を前向きに生きるためのサポートを大切にしています。そのために、患者さん個々の価値観や大事にしていることを尊重してケアしています。

医療行為は治癒を促進させる一方で、行為そのものが原因で感染を引き起こすことがあります。感染管理認定看護師は、患者・医療者を守るために、起こってしまった感染の拡大を防ぐと共に、感染させない為に、医師や薬剤師、検査技師などの専門家チームで活動しています。

糖尿病を持ちながら、他の病気の治療をする患者さんが増えています。日常生活と治療が密接な関係にある糖尿病患者さんがよりよい療養生活を送れるように、どの看護師も「糖尿病に強い看護師」になってもらいたいと思い、活動しています。

糖尿病看護外来でフットケアをしております。糖尿病は合併症が進行し足病変から切断にいたるリスクがあります。重症化を予防できるよう患者さんの思いを聴き、多職種と連携しながら患者さんの生活に合ったケアができるよう療養支援に努めています。

生殖医療を受けている患者さんは、治療方法の選択や仕事との両立など様々な悩みを抱えています。悩みを周囲に話せずに苦しんでいる方も多く、傾聴し、意思決定支援が行えるよう心掛けています。

私はリプロダクションセンターと、産婦人科外来・病棟で勤務しています。患者が納得して不妊治療に臨む事ができ、治療に対する不安が軽減するように努めています。また、産科外来や病棟では妊娠後の不安、第二子への期待など様々な葛藤に対して支援しています。

新生児医療の進歩で助けられる命が増え、後遺症なき生存に向け「すべては赤ちゃんと家族のために」を合言葉に新生児と家族に寄り添う看護を実践しています。NICUは新生児と親が家族としてスタートする大切な場所です。1番の味方でいたいと思っています。

一人ひとりの赤ちゃんに合わせた看護を提供するため、表情やしぐさを近くで見守りながら、赤ちゃんの持つ力を十分発揮できるようにサポートしています。言葉でコミュニケーションはとれませんが、温かい気持ちで声をかけながらケアを行うことを大切にしています。

小さく生まれた赤ちゃんや病気と闘う赤ちゃんの「生きる力」はとても力強く輝いています。
その個性あふれる生命力を信じて、成長・発達できるように支援させて頂いてます。
又、赤ちゃんとご家族の絆を大切により良く過ごせるように環境を提供していきます。

私は「患者さんにとっての善とは何か」ということを考え、患者さんの代弁者になれるように手術を受ける患者さんに看護ケアを提供しています。そして、手術チームのスタッフと話し合いながら質の高い手術看護を目指しています。

患者さんが手術を乗り越えて、日常生活に早く戻るためのサポートができるよう周術期看護を行っています。
周術期合併症のひとつである褥瘡予防にもスタッフと共に積極的に取り組んでいます。

進歩するがん医療を背景にがん患者さんの治療プロセスは長く複雑です。患者さんががんと共に自分らしく生きられるよう、患者さんの可能性を引き出すサポートは医療チームの大きな役割です。その為に、柔らかい心を持ち進歩し続けることを心がけています。

摂食・嚥下障害をもつ患者さんの、誤嚥性肺炎や低栄養などのリスクを回避して、安全においしく、“食べる”という希望を支えることを目標として取り組んでいます。毎日の活動では、多職種スタッフと協力し、チームとして最大限の力を発揮するように努めています。

患者・家族の望む「食べたい」という思いを叶えられるように、医師、言語聴覚士、栄養士と協働し、食事形態の調整や食事介助、栄養管理、口腔ケアなどの取り組みをしています。いつでも口から食べることができるように、病棟スタッフとともに日々の口腔ケアに力を入れています。

「小児救急」という一側面だけでなく、子どもの健やかな成長発達のために、ご家族も含めたケアを多職種と協働、連携しながら提供します。また、病院を受診した子どもへ専門的な知識と技術をもって看護ケアを行うと共に、子どもの声に耳を傾け「子どもの最善の利益」を保証します。

小児救急看護認定看護師の役割は、すべての子どもが健やかに育つことをサポートすることです。当院は、小児科病棟と外来が一体化となっており、外来受診時から入院、そして退院後も子どもとご家族をサポートできるような体制を整えています。ご家族の不安や心配事を一緒に考えながら、子ども成長を見守っていきます。また子どもの権利と安全を大切にしながら、質の高い看護を提供できるように目指しています。

入院の契機となった身体疾患だけでなく、患者さんとしっかり対話し、何を思い感じているかどういう人生を送ってきたかなど多角的に捉えるよう心掛けています。多職種で協働して認知症高齢者が安心して入院生活を送れるよう、そして家族も安心していただけるように取り組んでいます。

脳卒中は迅速な検査・治療により、後遺症を最小限に抑え、社会復帰できる病気です。そのため、院内研修を定期的に開催し看護の質の向上に努めています。患者さんが病気を受け止め、再発予防し、退院後に自分らしい生活が送れるよう看護ケアに努めています。

脳卒中は、時期に応じたプロセス管理が必要です。全身状態の観察を行いながら、安全に離床、リハビリを進めていくことで早期ADL回復が望めます。機能を再獲得していく過程に関われることに一番のやりがいを感じている為、患者さんの出来ることを引き出し、支えとなれるよう心掛けています。

患者さんとそのご家族が抱える不安を軽減し、放射線による有害事象を効果的に予防して、予定通りの治療が行えるように支援しています。
放射線治療にはチーム医療が欠かせません。チームで連携をとりながら、患者さんの思いを大切にした優しい医療を目指します。

心不全は増悪を繰り返しながら悪化します。塩分過多や怠薬、過活動が原因で心不全増悪するため、生活習慣を改善することで心不全増悪、再入院を予防することができます。多職種と連携し入院中から退院後の生活を見据えた生活指導を行い、外来でも継続し介入しています。

心不全増悪による再入院の回避・予防のため、個々の増悪因子を的確に評価し、入院中から退院後の生活に向けた療養支援ができるように介入・多職種間の調整を行っています。また、心不全外来で面談を実施し、病棟で行った療養支援内容の現状を確認し、継続看護を行っています。