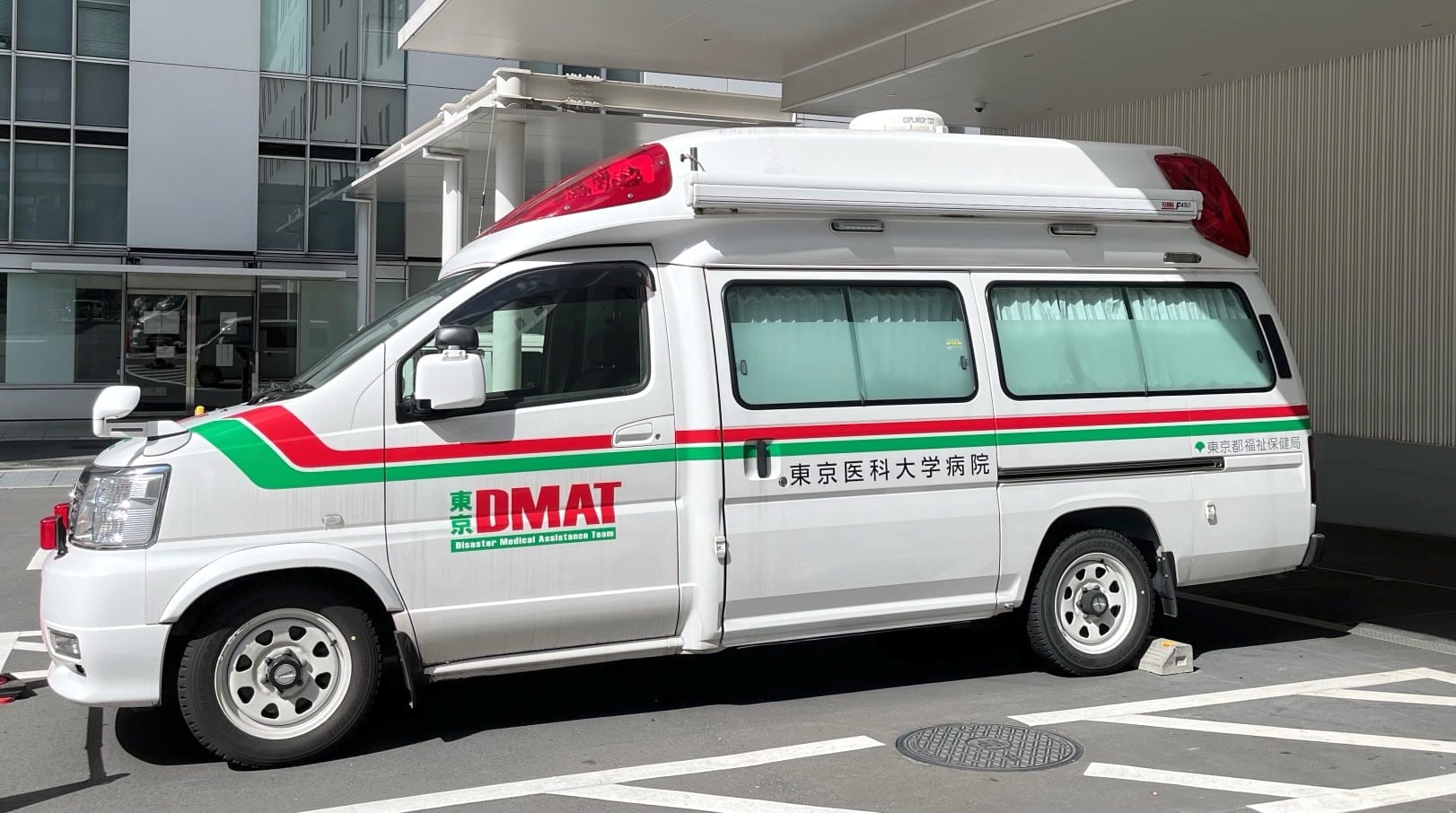肺・甲状腺の悪性・良性腫瘍の疾患が多く年齢層も10~90歳台と幅広いですが、その中でも高齢化社会に伴い70~80歳代の患者さんが、手術療法・薬物療法・放射線療法と多岐にわたる治療を受けています。胸腔鏡下・ロボット支援下手術による低侵襲手術やハイリスクな甲状腺手術を受ける患者も多く、薬物療法では新薬を多く取り扱っています。
それぞれの治療法に合わせたクリニカルパスを使用し、入院から退院までの統一した過程で医療と看護の提供を行っています。また、急性期から終末期と様々な病期の患者さんを対象としており、多職種カンファレンスにおいて患者さんの治療方針やQOLを考えたディスカッションを行い、患者さんのニーズに沿って医療従事者が同じ方向に進んでいけるよう日々検討を重ねています。
患者さんは、入退院を繰り返しながら社会生活を送り治療を継続しています。患者さんだけでなく家族の想いを汲み取り、笑顔と人を敬う気持ちを持って日々の看護をチームで考え看護実践に取り組んでいます。スタッフ間のコミュニケーションを大切にし、若いスタッフが段階的に成長できるようサポート体制を整えています。